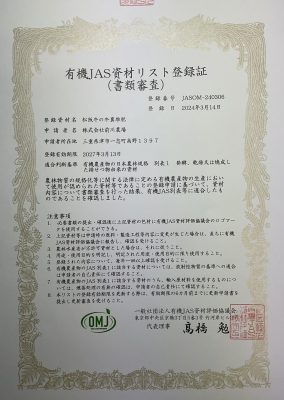第7回牧場雑学講座
皆さんこんにちは!
株式会社前川農場、更新担当の中西です。
今回は、個体毎の質についてです。
牛肉は、その柔らかさ、脂の入り方、風味の深さなどによって評価されます。一般的に「ブランド牛」や「A5ランク」といった言葉が注目されがちですが、実は同じ品種・同じ飼育環境で育った牛でも、一頭ごとに肉の質感は異なります。
なぜ牛によって肉の質感が違うのか?その秘密は、品種・育成環境・餌・ストレス・個体差といった複数の要素にあります。本記事では、食用牛の育成と肉質の関係について深掘りし、一頭ごとの違いが生まれる理由を詳しく解説していきます。
目次
1. 肉の質感を決める3つの要素
牛肉の「質感」は、主に柔らかさ・脂の質・赤身の風味の3つの要素で決まります。
① 柔らかさ(食感)
- 筋繊維の細さが影響する(細いほど柔らかい)。
- **脂肪の入り方(サシ)**によって、口どけが変わる。
- 運動量が多い部位(スネ・モモ)は筋繊維が発達し、硬めの食感に。
② 脂の質(霜降りの入り方・口溶け)
- 脂肪の融点(溶ける温度)が低いと口溶けが良く、なめらかな食感に。
- 牛の品種・餌の内容によって脂の質が変わる。
- 黒毛和牛は融点が低く、脂が甘くてまろやか。
③ 赤身の風味(肉の旨味・ジューシーさ)
- 筋肉中のミオグロビン量が多いほど、濃厚な風味になる。
- 運動量が多いと赤身のコクが増すが、肉質は硬めに。
- 穀物肥育の牛はまろやか、牧草肥育の牛は風味が強くなる。
同じ牧場で育てられた牛でも、これらの要素が微妙に異なるため、一頭ごとに異なる肉質になるのです。
2. 個体ごとに肉の質感が異なる理由
① 品種の違い
牛の品種によって、筋肉の付き方や脂の質が大きく異なります。
-
黒毛和牛(日本の高級和牛)
- 筋繊維が細かく、柔らかい肉質。
- 霜降り(サシ)が入りやすく、脂の質が良い。
- 甘みのある脂と、なめらかな舌触りが特徴。
-
ホルスタイン(乳牛の雄牛)
- 筋肉質で、赤身がしっかりしている。
- 霜降りは少なめで、赤身の旨味が強い。
- しっかりとした歯ごたえがあり、焼肉やステーキ向き。
-
アンガス牛(アメリカやオーストラリア産)
- 赤身と脂のバランスが良い。
- 霜降りは控えめだが、ジューシーな食感。
- 牧草肥育が多く、肉の風味がしっかりしている。
同じ育成環境でも、品種ごとの特性が肉質に大きく影響します。
② 飼育環境(運動量の違い)
牛が育つ環境によって、筋肉の発達具合や脂肪の付き方が変わります。
-
広い牧場で放牧されて育った牛
- 運動量が多いため、赤身が発達し、締まった肉質になる。
- 霜降りは少なめで、赤身の風味が強い。
-
狭い牛舎でストレスなく育った牛
- 運動量が少ないため、柔らかく、霜降りが入りやすい。
- 和牛は特にこの環境で育てられることが多い。
運動量の違いが、肉の締まり具合やサシの入り方に影響を与えます。
③ 餌(穀物 vs 牧草)
牛の餌は、肉質に大きな影響を与えます。
-
穀物(トウモロコシ・大豆など)主体の肥育
- 霜降りが入りやすく、まろやかな肉質に。
- 脂の融点が低く、口どけが良い。
- 和牛やアメリカの高級アンガス牛に多い。
-
牧草主体の肥育(グラスフェッド)
- 赤身が多く、肉の旨味が強い。
- 霜降りは少なめで、筋肉が発達するため歯ごたえがある。
- オーストラリアやニュージーランドの牛に多い。
同じ品種でも、餌の違いだけで肉の質感が大きく変わります。
④ 成長速度・肥育期間の違い
牛の肥育期間(何ヶ月間育てるか)によっても、肉質は変わります。
-
短期間(18~24ヶ月)の肥育
- 赤身が多く、霜降りは控えめ。
- 引き締まった食感で、肉の風味が強い。
-
長期間(30~36ヶ月)の肥育
- 霜降りが増え、肉が柔らかくなる。
- 和牛は長期肥育が一般的。
成長の仕方によって、肉の質感が大きく変わるのです。
3. 「同じ牛」でも部位によって質感が違う
牛の肉は、部位によっても食感が大きく異なります。
-
サーロイン・リブロース(背中側)
- 霜降りが入りやすく、柔らかい。
- 和牛の高級ステーキに最適。
-
ヒレ(腰の内側)
- 最も柔らかい部位で、脂が少なめ。
- 上品な味わいで、高級レストラン向き。
-
肩ロース・ウデ(前足側)
- ほどよい霜降りと、適度な歯ごたえが特徴。
- すき焼きや焼肉に向いている。
-
モモ・スネ(後ろ足側)
- 赤身が多く、しっかりした食感。
- 煮込み料理(ビーフシチューなど)に最適。
一頭の牛の中でも、肉質のバリエーションが豊富なのが特徴です。
4. まとめ——牛ごとに異なる「肉の個性」を楽しむ
食用牛の肉質は、品種・育成環境・餌・肥育期間・部位の違いによって大きく変わります。
✅ 和牛は霜降りが多く、まろやかで柔らかい。
✅ ホルスタインやアンガス牛は赤身がしっかりしている。
✅ 運動量が多いと締まった肉質、少ないと柔らかい肉質に。
✅ 穀物肥育は脂の質が良く、牧草肥育は赤身の旨味が強い。
「同じ品種の牛でも、個体ごとに肉の質感が違う」という奥深さを知ると、牛肉の楽しみ方がもっと広がります!
株式会社前川農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第6回牧場雑学講座
皆さんこんにちは!
株式会社前川農場、更新担当の中西です。
今回は、鉄則についてです。
食用牛の育成(牧場経営)は、牛の健康管理・飼料の選定・環境の最適化を徹底することで、高品質な牛肉を生産する重要な仕事です。特に、和牛の育成は世界的にも高度な技術が求められ、肉質や風味を決定づける要素が細かく管理されています。
1. 食用牛育成の基本原則
食用牛の育成は、以下の3つの基本原則に基づいて行われます。
✅ ① 健康管理の徹底
- 牛の病気やストレスを防ぎ、健やかな成長を促す。
✅ ② 適切な飼料と栄養バランス
- 肉質を決定づける要因として、栄養価の高い飼料を適切に与える。
✅ ③ 環境の最適化
- ストレスフリーな飼育環境を整え、牛の成長を促す。
これらを実践することで、高品質な牛肉を生産し、市場での競争力を高めることができます。
2. 食用牛育成(牧場)の鉄則
鉄則① 健康管理の徹底
牛の健康を守ることは、育成の最も基本的かつ重要な要素です。病気やストレスが牛に与える影響は大きく、肉質の低下や生産効率の悪化につながります。
✅ 適切なワクチン接種・感染症予防
- 牛はウイルスや細菌に感染しやすいため、定期的なワクチン接種が必須。
- 代表的な予防すべき病気:口蹄疫(こうていえき)、牛ウイルス性下痢症(BVD)、肺炎 など。
✅ ストレスの軽減
- 牛はストレスを受けると、免疫力が低下し、病気になりやすくなる。
- 人間の接し方、放牧環境、温度管理などを適切に行う。
✅ 適切な運動の確保
- 放牧を取り入れることで、筋肉の発達を促し、健康な肉質を形成できる。
- 特に黒毛和牛では、適度な運動が霜降り(サシ)の形成に重要。
🚨 注意点
- 牛がストレスを受けると、硬い筋肉が形成され、肉質が落ちる。
- 急激な気温変化や騒音環境は避ける。
鉄則② 適切な飼料と栄養バランス
飼料は、牛の成長や肉の味に大きな影響を与えます。特に和牛は、飼料の内容が肉の甘みや霜降りの質を左右するため、細かい管理が求められます。
✅ 成長段階に応じた飼料の設計
-
哺育期(生後0~3ヶ月)
- 初乳(母乳)を十分に摂取させ、免疫力を高める。
- 早めに「スターター飼料(栄養価の高いペレット)」を導入し、胃の発達を促す。
-
育成期(生後3~10ヶ月)
- 繊維質(牧草・乾草)を多く含む飼料を与え、消化器官を発達させる。
-
肥育期(生後10ヶ月~出荷前)
- 穀物中心の飼料(トウモロコシ、大豆かす、ふすま)を増やし、脂肪を蓄積させる。
- ビール粕やオリーブ粕を混ぜることで、肉質の向上につながる。
✅ こだわりの「特別飼料」
- 但馬牛(神戸牛)→ 酒粕を配合し、風味を強化。
- 松阪牛 → 大豆・トウモロコシ中心で霜降りを増やす。
- 飛騨牛 → ミネラル豊富な天然水を与え、肉質を柔らかくする。
🚨 注意点
- 栄養バランスが崩れると、脂肪がつきすぎたり、肉質が硬くなったりする。
- 飼料の品質管理を徹底し、カビや有害物質の混入を防ぐ。
鉄則③ ストレスフリーな環境の確保
牛はストレスを感じると、肉質が低下し、病気になりやすくなるため、牧場環境の管理が重要です。
✅ 適切な飼育スペースの確保
- 1頭あたりの適正スペースを確保(約5~10㎡)し、牛同士の接触ストレスを軽減。
- 過密飼育を避け、十分な運動スペースを確保する。
✅ 温度と湿度管理
- 夏場は遮光シェルターや冷却ファンを設置し、熱ストレスを防ぐ。
- 冬場は適度な保温対策を施し、寒さによる成長遅延を防ぐ。
✅ 静かな環境の確保
- 大きな騒音や急な環境変化は牛にとって大きなストレス。
- トラックや機械音が多いエリアでは、防音対策を行う。
🚨 注意点
- 環境が悪いと、牛が攻撃的になり、ケガや肉質低下の原因になる。
- 衛生管理を怠ると、病原菌が繁殖しやすくなる。
3. まとめ
食用牛の育成(牧場運営)は、適切な健康管理・飼料・環境の3つの要素を徹底することで、高品質な牛肉を生産できる。
✅ 鉄則① 健康管理の徹底
- 定期的なワクチン接種、適切な運動、ストレス軽減。
✅ 鉄則② 適切な飼料と栄養バランス
- 成長段階に応じた飼料管理と、高品質な特別飼料の導入。
✅ 鉄則③ ストレスフリーな環境の確保
- 飼育スペース・温湿度管理・騒音対策を適切に行う。
これらの鉄則を守ることで、牛は健康に育ち、最高級の肉質を持つ「和牛ブランド」として市場で高い評価を受けることができる。持続可能な畜産の実現と、国際競争力の向上のためにも、最新技術と伝統的な飼育方法を融合させながら、より良い牧場運営を目指していくことが求められる。
株式会社前川農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第5回牧場雑学講座
皆さんこんにちは!
株式会社前川農場、更新担当の中西です。
今回は、歴史についてです。
日本における食用牛の育成は、現在の「和牛ブランド」として世界的に評価されています。しかし、その歴史を振り返ると、日本人が牛肉を食べるようになったのは比較的最近のことであり、もともとは農耕や運搬のために牛が飼育されていました。
目次
1. 日本における牛の飼育の起源
① 古代(弥生時代~奈良時代):牛は農耕用・祭祀用
牛が日本に伝来したのは、弥生時代(紀元前300年~300年頃)とされ、主に農耕や運搬のために飼育されていました。
✅ 牛の伝来
- 朝鮮半島を経由して日本へ。
- 弥生時代の遺跡から牛の骨が発見されており、農耕用として使われた可能性が高い。
✅ 奈良時代(8世紀)
- 仏教の影響で、肉食が禁止される。
- この頃の牛は「使役牛」として、農作業や荷物の運搬が中心。
- 牛乳を飲む習慣は一部の貴族の間であったが、一般には広まらなかった。
2. 中世~江戸時代:牛肉禁止と隠れた食文化
① 中世(平安時代~戦国時代):牛肉の食文化が制限される
✅ 仏教の影響と肉食禁止令(675年)
- 天武天皇が「殺生を避けるために肉食禁止令」を発布。
- 以降、江戸時代までの長い間、牛肉を食べる習慣は表立って広まらなかった。
✅ 一方で密かに続いた牛肉食
- 西日本の一部地域(近江、但馬、播磨など)では「薬食い」として牛肉を食べる風習が残る。
- 滋賀県近江地方では、病気の治療や滋養強壮のために牛肉を食べる「養生食」として扱われていた。
② 江戸時代(1603年~1868年):隠れた牛肉文化と和牛のルーツ
江戸時代になると、各地で在来種の牛(後の和牛のルーツ)が農耕用に発展し、日本独自の牛の品種が生まれました。
✅ 江戸時代の牛の特徴
- 「但馬牛」「近江牛」「土佐赤牛」など、各地で異なる牛の品種が発展。
- ほとんどの牛は農耕や荷役用で、食用としての認識は低かった。
✅ 「すき焼き」文化の萌芽
- 近江(現在の滋賀県)では、僧侶や医者が牛肉を食べる習慣があった。
- 「味噌漬け牛肉」などの調理法が考案され、後のすき焼き文化につながる。
3. 明治時代~戦後:食用牛の本格的な発展
① 明治時代(1868年~1912年):食肉文化の解禁
✅ 明治政府の「肉食推奨政策」
- 1872年、明治天皇が牛肉を食べたことが話題となり、日本国内で「肉食文化」が拡大。
- 西洋文化の影響を受け、牛肉が「栄養価の高い食品」として注目される。
- 東京・大阪に牛鍋(すき焼き)の専門店が登場し、大衆にも広がる。
✅ 食用牛の品種改良の開始
- 明治政府は、海外の牛(欧米のショートホーンやブラウンスイス)を導入し、在来種と交配。
- この時期に、但馬牛や近江牛などが改良され、現代の和牛の基礎が確立。
② 戦後~高度経済成長期(1945年~1970年):和牛ブランドの確立
✅ 戦後の食肉需要の増加
- 戦後の復興とともに、食肉消費量が急増し、牛肉の生産が本格化。
- 1950年代以降、アメリカの影響でステーキ文化が広がる。
✅ 「和牛」のブランド化
- 1960年代:但馬牛をベースにした「神戸牛」「松阪牛」などのブランド和牛が誕生。
- 1970年代:霜降り肉(サシ)の技術が発展し、「柔らかくて甘い和牛」が高級ブランドとして確立。
4. 現代の食用牛産業と課題
① 日本の食用牛の品種
現在、日本で食用として育成される牛は、大きく分けて以下の3種類。
✅ 和牛(国産黒毛和種)
- 「神戸牛」「松阪牛」「飛騨牛」など、最高級ブランド牛肉として扱われる。
- 肉質が柔らかく、霜降りが豊富で甘みが強い。
✅ 交雑種(和牛×乳牛)
- 育成コストを抑えつつ、一定の品質を確保。
- スーパーなどで流通する一般的な国産牛肉。
✅ ホルスタイン種(乳牛)
- 乳牛として飼育された後、一部が食用肉となる。
- 赤身が多く、脂肪分が少ないのが特徴。
② 現代の課題
✅ 生産コストの上昇
- 飼料の高騰や人件費の増加により、和牛の価格が高騰。
- 海外産牛肉との価格競争が激化。
✅ 輸出市場の拡大
- 和牛は海外での人気が高まり、特にアメリカ・中国・シンガポールなどで需要が増加。
- 高品質な和牛の安定供給が求められる。
✅ 持続可能な畜産への移行
- 環境負荷を抑えるための「低炭素畜産」や「放牧型畜産」の導入が進む。
5. まとめ
✅ 古代~江戸時代:牛は農耕用で、食用としては限られていた。
✅ 明治時代~戦後:肉食文化が定着し、和牛の品種改良が進む。
✅ 高度経済成長期~現代:ブランド和牛が確立し、輸出市場が拡大。
✅ 今後の課題:持続可能な畜産と価格競争への対応。
日本の食用牛の育成は、長い歴史の中で進化し、「和牛ブランド」という世界に誇る食文化を築き上げました。今後も、環境問題や国際競争の中で、持続可能な形での発展が求められています。
株式会社前川農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第4回牧場雑学講座
皆さんこんにちは!
株式会社前川農場、更新担当の中西です。
本日は第4回牧場雑学講座!
今回は、季節ごとの牧場作業についてです。
季節ごとの牧場作業と動物のケア
牧場の作業は季節によって変わります。
春夏秋冬それぞれの季節に応じて、動物たちのケアや牧草地の管理が異なります。
この回では、季節ごとの牧場作業や動物のケアについて、詳しく解説します。
季節ごとの作業
春の作業:放牧開始と出産シーズン
春は放牧が始まり、動物たちが外で新鮮な草を食べる季節です。
特に羊や牛の出産シーズンであるため、母親と子供の健康管理に気を配り、体調をチェックします。
また、放牧地のフェンスや草地の整備も行います。
夏の作業:熱中症対策と水分管理
夏は暑さ対策が重要です。
動物が日陰で休めるように環境を整え、水を十分に与えます。
特に乳牛は熱中症のリスクがあるため、風通しの良い場所に移動させ、頻繁に健康状態を確認します。
秋の作業:牧草の収穫と冬支度
秋は牧草を収穫し、冬の飼料を確保する季節です。
また、動物たちが寒い冬を快適に過ごせるよう、飼育施設の修繕や防寒対策を行います。
秋は動物が体重を増やし、栄養を蓄えるための重要な時期です。
冬の作業:室内での飼育と健康管理
冬は気温が下がるため、多くの動物が室内で過ごします。
飼育施設の暖房を管理し、風邪や病気にかからないよう、栄養価の高い餌を与え、健康を維持します。
寒さによるストレスを軽減し、動物たちが快適に冬を越せるように配慮します。
以上、第4回牧場雑学講座でした!
次回の第5回もお楽しみに!
株式会社前川農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第3回牧場雑学講座
皆さんこんにちは!
株式会社前川農場、更新担当の中西です。
本日は第3回牧場雑学講座!
今回は、動物の飼育方法についてです。
動物の飼育方法と育成のポイント
動物たちが健康に成長し、安心して生活できる環境づくりは牧場経営の基本です。
この回では、乳牛、馬、羊、ヤギなど、牧場で飼育される動物の特徴に合わせた飼育方法や、育成のポイントについて詳しく説明します。
動物ごとの飼育方法
乳牛の飼育方法
乳牛は栄養バランスの取れた餌と、快適な生活環境が求められます。
乳の品質を保つために、毎日搾乳することや、健康管理が大切です。
また、牛舎を清潔に保ち、風通しを良くすることでストレスを軽減し、牛が快適に過ごせるよう工夫します。
馬の飼育方法
馬は運動量が多く、放牧や広い運動場が必要です。
また、馬には専用の飼料を与え、体重管理や蹄の手入れも欠かせません。
健康な体を維持するため、馬の毛づやを保ち、定期的に獣医の健康チェックも行います。
羊とヤギの飼育方法
羊やヤギは比較的丈夫で、放牧しながら育てることができます。
放牧地の草が豊富であれば、自然に近い環境で育てられ、ストレスも少なくなります。
また、羊毛の収穫やミルクの生産を行う場合、毛の手入れや搾乳の管理も重要です。
その他の動物
他にも、牧場によっては鶏やウサギを飼育している場合があります。
鶏は毎日卵を産み、ウサギはその愛らしさから観光牧場の人気動物として大切に育てられています。
以上、第3回牧場雑学講座でした!
次回の第4回もお楽しみに!
株式会社前川農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第2回牧場雑学講座
皆さんこんにちは!
株式会社前川農場、更新担当の中西です。
イベント盛り沢山なこの季節、いかがお過ごしでしょうか?
さて、本日は第2回牧場雑学講座!
今回は、牧場の日常業務についてです。
牧場の日常業務とは?
牧場で働く人々は、朝から晩まで家畜のお世話をしています。
牧場の業務は、動物の健康管理や餌やり、搾乳などさまざまな作業で構成されています。
この回では、牧場で行われる日常業務やルーチン作業について、詳しく解説します。
毎日の業務内容
餌やりと給水 毎朝、動物たちに新鮮な餌と水を提供するのが基本的な仕事です。
乳牛には栄養バランスのとれた餌が与えられ、羊やヤギは放牧で自然の草を食べることもあります。
動物の成長段階に合わせて餌の内容や量を調整することで、健康的に育てることができます。
健康チェックと記録
動物の健康管理は毎日の業務で最も重要です。
動物が元気に活動しているか、食欲や毛艶、排泄の様子をチェックします。
また、体温や体重を定期的に測定し、体調の変化を早期に発見できるよう記録をとります。
搾乳作業
乳牛や山羊から毎日搾乳する作業は、牧場のメイン業務です。
搾乳は通常朝と夕方に行われ、手作業や搾乳機を使用します。
清潔な環境で行われる搾乳は乳の品質を保つために重要で、搾乳後は速やかに冷却し、衛生管理を徹底します。
清掃と環境整備
牧場内は清潔な状態を保つことが重要です。
家畜舎の掃除や糞の処理、餌場や水飲み場の洗浄を行い、衛生的な環境を整えます。
また、糞は堆肥として再利用することで、循環型の農業を実現しています。
以上、第2回牧場雑学講座でした!
次回の第3回もお楽しみに!
株式会社前川農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第1回牧場雑学講座
皆さんこんにちは!
株式会社前川農場、更新担当の中西です。
いよいよ寒くなってきましたが、皆さん元気に過ごされていますか?
風邪をひかないよう、防寒対策を徹底していきましょう!
さて、本日からシリーズ更新が始まります!
株式会社前川農場監修!
牧場雑学講座!
記念すべき第1回目のテーマは!
牧場とは?
牧場の役割と日々の生活についてです!
牧場は、牛や馬、羊、ヤギなどの家畜を育て、乳製品や肉製品の生産、観光などを行う場所です。
牧場は、自然との共生の場であり、また、サステナブルな農業の一環として地域社会にも貢献しています。
この回では、牧場の基本的な役割と、日々の生活について詳しく解説していきます。
牧場の役割
牧場は動物たちが自然に近い環境で生活しながら成長し、乳や肉といった食品の生産が行われる場所です。主に以下のような役割があります。
乳製品や肉製品の生産
乳牛や山羊などから搾乳を行い、牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品が生産されます。また、育てた家畜の肉を出荷し、肉製品として消費者に届けることも牧場の大切な役割です。品質の良い乳や肉を生産するために、健康管理や飼育環境の整備が欠かせません。
観光牧場としての役割
近年、観光牧場も増えており、牧場が訪問者に動物とのふれあい体験や乳搾り、餌やりなどのアクティビティを提供することで、観光地として地域に貢献しています。観光牧場では、都市部に住む人々に農業や動物の生活を知ってもらう教育の場としての役割も担っています
自然保護とサステナビリティ
牧場の多くは自然豊かな環境にあり、牧草地や森林を維持しながら牧畜を行います。持続可能な農業の一環として、動物の糞や牧草地の管理が環境に配慮した形で行われ、自然の生態系が保たれるよう努めています。
以上、第1回牧場雑学講座でした!
次回の第2回もお楽しみに!
株式会社前川農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
2023年4月2日㈰ 肉亭 ナカムラにて会食 隣の席には○○さんが・・・
2023年4月2日㈰ 株式会社中村畜産 直営店 肉亭 ナカムラに伺いました。
埼玉県越谷市北越谷2丁目20−16
WQ2H+FQ 越谷市、埼玉県
https://nikutei-nakamura.com/about.html


中村会長・社長・部長の手厚いおもてなしを頂きました。
さらに、中村会長自らお肉を焼いて頂きました。
お肉の焼き加減を見つめるお姿、男前でした。
中村社長とは、今後の方向性・ご意見などを頂きました。
親身になって接してくださり、ありがとうございました。


中村部長、お客様が多くいらっしゃる中
子どもたちにも気さくに声をかけてくださり、ありがとうございました。
皆さん、是非とも 肉亭 ナカムラ にお越しください。
まだ終わりません。
今回は、なんとお隣に芸人さんのクールポコさんがいらっしゃいました。
中村会長・社長・部長とは古くからの付き合いだそうです。
皆さん、お肉を美味しく頂いておりました。

撮影・ブログ投稿にも心よくお引き受けて頂きました。
クールポコさん、ありがとうございました。
宣伝です
クールポコさんの経営するBARがあります。
名前は、「せんbar」です。
〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目17−10 プランドール壱番街 3F
https://www.facebook.com/senbar.2016.0912/
皆さんお時間があるようでしたら、お越しください。